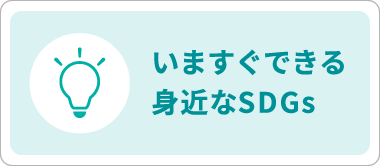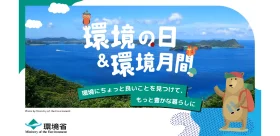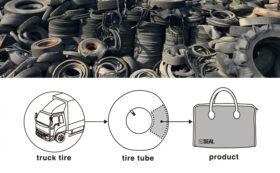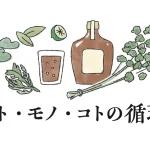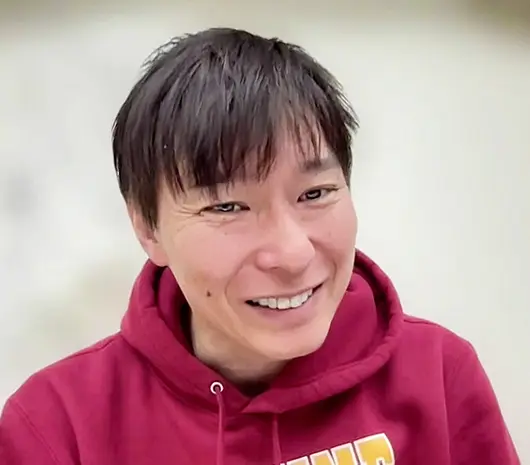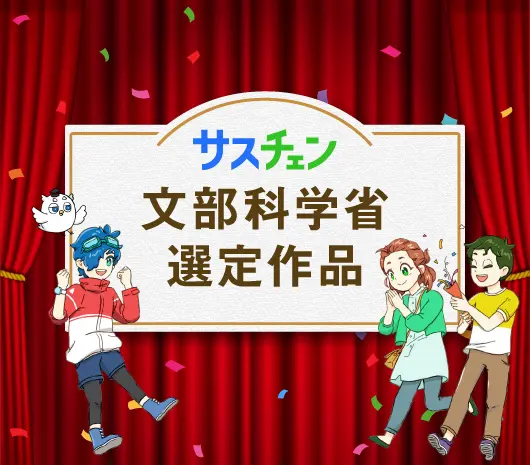冷蔵庫の整理整頓からはじめよう!食品ロス対策
日本では、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」の量が年間522万トン(※1)もあると言われています。
「食品ロス」は、食品メーカーやスーパーマーケットなどで発生していると思いがちですが、約半分は家庭から発生しています。
その量を国民ひとりあたりに換算すると、お茶碗約1杯分(約113g)の食べものが毎日捨てられていることになるのです。
今回はそんな家庭での「食品ロス」を減らすためにできることについてご紹介します。
家庭で発生する食品ロスとは?
家庭からの食品ロスの要因は、大きく3つに分類されます。(※2)
①料理を作りすぎて残る「食べ残し」
②野菜の皮や茎など食べられるところまで切って捨ててしまう「過剰除去」
③未開封のまま食べずに捨ててしまう「直接廃棄」
このような家庭での食品ロスを減らすためには、買い物の際、料理の際、食事の際にそれぞれ少しだけ意識したり、工夫したりすることが大切です。
※2 消費者庁食品ロス削減特設サイト「家庭での食品ロスを減らそう」

食品ロスを減らすためにできることは?
家庭で食品ロスを減らすコツは、買い物の際は「必要な分だけ買う」、料理の際は「食べきれる量を作る」、食事の際は「おいしく食べきる」ことが大切です。
【買い物編】
まずは買い物に行く前に冷蔵庫や食品庫にある食材をチェックしましょう。
買うものをメモしたり、冷蔵庫の写真をスマホで撮影したりすると在庫がしっかり把握できるため、余計な買い物を減らすことができます。
買い物をする時はまとめ買いを避け、使う分、食べられる量だけ買うことを意識しましょう。
また、すぐに使う予定の食材は期限の長い商品を選択するのではなく、陳列順に取ることで、お店の食品ロス削減に貢献できます。
【料理・保存編】
料理の際は、食べきれる量を作るようにしましょう。
もし作りすぎてしまった場合はリメイクレシピなどで工夫するとおいしく食べきることができます。
また、食材が余ったときには、食材を冷凍保存すると上手に使い切ることができるのでおすすめです。
「野菜の冷凍保存で食品ロスを減らそう!」の記事でも紹介していますので参考にしてみてください。
さらに消費者庁では料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」において食材を無駄にしないレシピも紹介されています。
【食事(外食)の時】
自身や家族で食べきれると思う量を注文し、どうしても食べきれない場合は持ち帰ることができるかどうかお店の方に確認してみましょう。
また、持ち帰る際にはその後の予定、季節などを考慮して、お店の方に注意事項をしっかり確認しておきましょう。
冷蔵庫の整理整頓で食品ロスを減らそう
食品ロスを減らすために、買い物・料理・食事の3つのシーンに分けてご紹介しましたが、なにから始めるか迷ったらまずは冷蔵庫の整理整頓がおすすめです。

「冷蔵庫の奥から賞味期限切れの食材が出てきた」「中身がひと目でわからずに同じものを買ってしまった」ということが起こらないよう、週に1回「冷蔵庫のお片付け」を行いましょう。
冷蔵庫の整理整頓のコツ
1.食品を種類(カテゴリ)分けする
2.それぞれの置く場所を決める
3.フリースペースを作る(冷蔵庫に保存する食材は7割以下にしましょう)
4.ストックのルールを決める
なお、消費者庁作成の食品ロス削減啓発冊子「計ってみよう!家庭での食品ロス」の10、11ページ(PDF6枚目)にも詳しい整理整頓のコツが図で解説されていますので参考にしてみてください。
普段なんとなく捨ててしまっている食品は、すべて食品ロスに繋がっています。
一人ひとりがもったいないという気持ちを大切に、買いすぎない、作りすぎないことを意識することで食品ロスを減らしていきましょう。
----------------------
----------------------

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。
他の記事を見る

OTHER ACTION