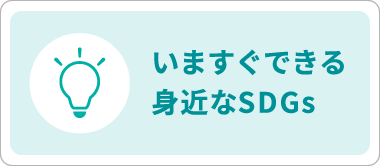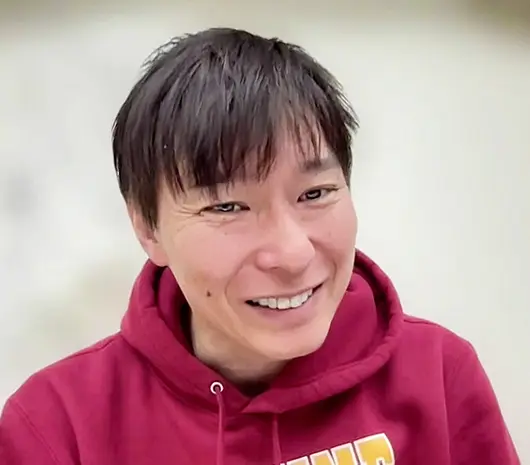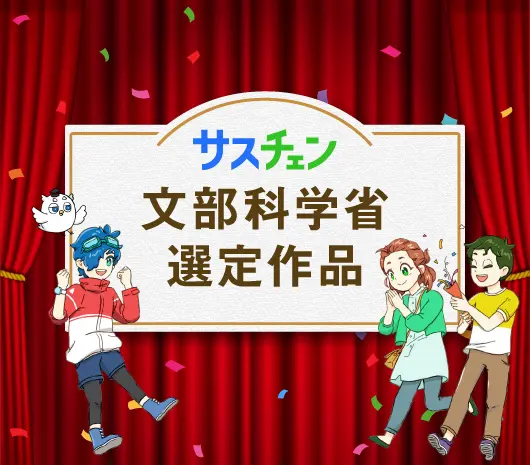海が気候危機を救う鍵となるのか?持続可能なソリューションとその実装課題──ワールド・オーシャン・サミット総力特集第7弾
2025年3月12〜13日に開催された、世界の海洋課題を議論する国際会議「第12回ワールド・オーシャン・サミット」。本特集は、その模様を多角的にお届けするレポートシリーズの第7弾です。
地球温暖化の影響が海洋に深刻な影響を及ぼすなか、同時に海自体が気候変動の解決策として注目されています。
今回は「海洋気候ソリューション」の可能性と課題についての議論をお届けします。
ワールド・オーシャン・サミットとは
ワールド・オーシャン・サミットは、持続可能は海洋経済に向けた行動を起こすことを目的に、世界中の政策立案者、ビジネスリーダー、科学者、NGO、技術開発者、投資家などが集結し、海洋環境を保護しながらも経済的に発展させる方法について議論する場です。

「海洋気候ソリューションと今後の展望」概要
海洋における気候変動の影響が深刻化する一方で、海洋が気候危機そのものを緩和する機会を提供しています。
持続可能な海洋経済に関するハイレベル・パネルの報告書では、産業革命以前の状態から地球の気温上昇を1.5℃以上抑制するというパリ協定の目標を達成するために必要な排出削減量の最大35%を海洋が提供できる可能性があると推定しています。
政策に重点を置いたアプローチでは、気候に関する制度上の枠組みに海洋を統合する取り組みを拡大することのメリットが強調されています。
海洋と気候に関する解決策はどのような進展を見せているのでしょうか?海洋における気候変動の影響が深刻化する中、対応はそれに追いついているのでしょうか?
■司会
・シャーロット・ハワード氏 ザ・エコノミスト エグゼクティブ・エディター兼ニューヨーク支局長
■パネリスト
・キラパルティ・ラマクリシュナ氏 ウッズホール海洋研究所海洋・気候政策ディレクター
・M. サンジャヤン氏 コンサベーション・インターナショナル最高経営責任者
・イラナ・セイド氏 パラオの国連大使兼常駐代表
・エリザ・ノースロップ氏 ニューサウスウェールズ大学持続可能な開発改革センター所長


各分野との連携
シャーロット・ハワード氏 (ザ・エコノミスト エグゼクティブ・エディター兼ニューヨーク支局長)
海洋が提供する可能性のあるいくつかの解決策について見ていきましょう。解決策とは、「海洋が進行中の気候危機の解決にどう貢献するのか」ということです。
それではまず「ビジョンベースのソリューション」というと具体的には何を意味するのか、お話しいただけますか?

キラパルティ・ラマクリシュナ氏 (ウッズホール海洋研究所海洋・気候政策ディレクター)
それは一種のラベルのようなものです。気候変動の原因は何なのか、どのように削減が必要なのかを見極めなくてはなりません。
私たちはあらゆる影響要因を考え抜く意志を当初は持っていませんでした。それが、これを実存的脅威と呼んでいる理由の一つです。私たちは、従来は異論が出てこなかったような海洋にまつわる認識のすべてを検証していくつもりです。

これまで私たちは気候分野にそれほど注力してこなかった時間が長かったのですが、ここ数年ようやく取り組みを始めました。ただ、今は「海洋のどの部分がどのように役立つか」を考える段階を越えなくてはいけません。
とりわけ、私たちが長年取り組んできた分野全体にわたる連携が重要です。気候への献身、適応であれ緩和であれ、あるいは沿岸コミュニティを支援することであれ、自宅レベルだけでは不可能なものを、広い視野で進めることが必要です。
シャーロット・ハワード氏
ありがとうございます。それでは、スケーリングアップする上での障壁について少しお話しいただけますか?
M. サンジャヤン氏 (コンサベーション・インターナショナル最高経営責任者)
一部の国や沿岸地域における資金調達メカニズムの問題があります。現時点での計画は十分とはいえません。

だから、私が言う「永久的な損失と回復」が子どもたちの世代で起こってしまうような、非常に厳しい環境にある地域に目が向きがちです。そこにはマングローブや海草藻場などが含まれます。
世界の南側には、面積的には1~2%ほどのごく一部しか占めていない地域でも、世界全体の炭素排出量の約10%に関わるようなケースがあるのです。
まさに大学の研究からも見えるように、今この瞬間に「地球の温度を下げる・パニックを抑える」ためには、マングローブや海草藻場を保護・再生することが最も効果的でしょう。おそらく私たちの生活を守る手段としても最有力なのです。
しかし課題もあります。現場には取り組む力がある一方で、政府はこの問題にどう対応するか合理的な政策枠組みを整える必要があります。
現実的には多くの場合、通常の仕組みや規則だと「データを提出して契約者に支払いをし、問題を解決する」というような単純化されたゲームルールしか存在しないのです。
取り組みをどう実行するかに対して資金を払う必要があり、そこで初めて具体的なプロジェクトが目に見えてきます。これが第一のステップです。次に必要なのが方法論です。
要は、全体の論理を分断するわけではなく、地中や海底下にあるものを測定するための手引き的な論理体系が必要になります。今まさにそれをどう実現するかという手法を探っているところです。
オーストラリアでも今、かなりローカルレベルで進んでいます。私たちもいくらか作業を行っています。ただ、まだ公表されていない研究もあります。 実証可能な方法があるのです。
ただし長期的なシステムを理解するための費用も必要で、そこで何が起こるのかも把握する必要があります。
どんな突飛なプロジェクトでも、将来的に利益が出ると投資家コミュニティに示せば資金は集まりやすいものです。将来大きなリターンがあると説得することで、事実上多くの人を動かせるのです。

炭素に関しては、その価値がますます明白になってきていると思います。将来に向けた新しいカーボンシステムは、今よりも将来のほうがさらに価値が高まるはずです。
正確な実証はまだ完璧でなくとも、われわれは一定の効果を出せることを知っており、いずれそれに応える動きが出てくるでしょう。
今後、AIの進展もありますが、それ以上にコミュニティの参加がどれほど加速できるかが鍵だと考えています。大規模なカーボンプロジェクトの多くは、先住民や地元コミュニティの所有地で行われる傾向にあります。そこで生まれる収益の50%は、そうしたコミュニティに属します。
しかし、それが国の政策とは上手くかみ合わない場合もあり、国側が大半の利権を握ってしまうこともあります。さらに大きな課題は、コミュニティの中にじっくりと時間をかけて入り込み、彼らがまず何を失敗と思っているのか、それをどう乗り越えるのかを十分理解してもらうことです。
彼らには、これらの地域を回復・保護し、長期的な対策に取り組むだけの大きな力があります。
実際にそういう事例は存在しますし、広がりつつあります。ただ、時間がかかるのです。


海洋と気候政策
シャーロット・ハワード氏
先ほどの論点にもありましたように、合理的な政策フレームワークというのは必ずしも流行りではないかもしれません。
今の政治状況を考えても、高い優先度を装うようなものではないのかもしれませんが、なぜそうなっているのでしょう?
そして、より専門的な政策フレームワークへ進むための道筋はあるのでしょうか。
イラナ・セイド氏 (パラオの国連大使兼常駐代表)
私たちが行った統計によると、海洋が気候変動緩和の観点から一つの解決策となる可能性はかなり高いという結果が出ています。

そしてビジョンに基づく取り組みがあり、私もそのプロセスに関わりました。2023年にプランニングコミッションの委託を受けて作成した報告書を更新してきましたが、それは間違いなく有効です。
まず、私たちが2019年から2022年にかけて取り組んだことですが、当時は自然ベースのソリューションや保全アジェンダ以外で、海洋がどう緩和に貢献するかについての議論は多くありませんでした。
長い間、そうした話はあったものの、当時は「ニッチな課題」「自然保護の文脈だけの問題」と見なされていたのではないかと思います。
そして2019年に最初の報告がなされたとき、私たちはこれをより幅広い「自然ベースのソリューション」として再評価したのです。海洋のエネルギーに特化した注目が必要だと強く感じました。

そして「ゴールドスタンダード」を使うことについても。残念ながら多くの人はまだ海洋に強い感情を持っていません。
ここにいる多くの人も「自分たちはどう海とつながっているのか」と疑問を抱いているでしょう。
しかし、多くの国やコミュニティでは、追跡可能な選択肢に注目しています。長い間、こうした分野は輸送やエネルギー安全保障と切り離されてきました。
海洋経済がもたらす機会は、とりわけ大国にとって非常に大きいのです。これは単なる排出削減の義務という視点だけではありません。
もちろんそれも極めて重要ですが、資金モデルを確立すること、技術支援やサポートを得て、どのようにネットゼロへ移行するかを考える必要があるのです。
変化が始まっているのは確かだと思いますが、これは特別な問題でもなんでもないという事実を忘れてはなりません。保全アジェンダの文脈の中に実際の大きなチャンスがあり、そこを新たな政策や仕組みに移行させる必要があります。
技術的・資金的な支援も必要です。これは非常に大きな作業で、2019~2020年以降、私たちはかなり進歩してきましたが、それでも道のりはまだ長いです。


資金面での問題も
シャーロット・ハワード氏
ここで注目度の問題について少し触れたいのですが、気候アジェンダは非常に広範囲ですし、多くのステークホルダーがそれぞれ別の課題に取り組んでいます。
小島嶼開発途上国(SIDS)は常に最前線に立たされてきたわけですが、他の国々が自国の排出削減目標やコミットメントを達成するために必要とされる支援について、どのようにお考えでしょうか?
私たちには活用できるチャンスがあるのではないですか。
エリザ・ノースロップ氏 (ニューサウスウェールズ大学持続可能な開発改革センター所長)
国際的なレベルで私たちが取り組んでいることの文脈で申し上げると、もしこのままの状態が続けば、時間の経過とともに国そのものが存続できなくなるという大きな課題を抱えている国がある、ということを繰り返し訴える必要があるのです。
5年後には消えてしまうかもしれません。

ですから、私たちが米国で行っているアドバイザリー業務の一部は、気候変動の緩和策についての対話を進めることで、自然を基盤とした解決策を提唱することでもあります。例えば海草や藻場の保護などです。
しかし同時に、国内レベルでも課題を抱えています。私たちはODAにも頼ってきましたし、開発援助も受けています。とはいえ、資金面が大きな課題です。
現状、全体の金融支援のうち2%しか回ってきていない。機関としては20%ほどの投票権(あるいは発言権)を得ているという状況ですが、世界の海の30%を管轄している39の国々がある一方でそこには大きなギャップが存在しているのが分かるでしょう。
まだ十分に予算が割り当てられているとは言えません。そういう問題ではないのです。 それは多くの省庁間の問題を前面に突きつけることでもあります。
海洋は最大の炭素吸収源であり、二酸化炭素や余剰熱を抱え込んでいる一方で、膨大な経済活動と多くの協力関係も生み出しています。
これは、1.5度目標を達成するために必要な取り組みのうち、35%を実現できる可能性がある解決策です。世界の排出量の80%を占めるG20には、実効的な削減策を取ってもらわないと、私たち小島嶼国が存続することは難しいです。同時に、自分たちが競争力を失わず、認証などを得られるような仕組みも必要です。


保全は利益につながる
シャーロット・ハワード氏
直観的に取り組みやすい例がいくつかあるかと思いますが、それについて全体像をお話しいただけますか?
さらに、どのように規模拡大が可能かという点にも触れていただきたいです。
キラパルティ・ラマクリシュナ氏
ありがとうございます。最近では、多くのレポートや映像、書籍などが公開されています。
米国でも、どのような確固たる証拠があるのかを詳細に調べる動きが進んでいます。一方でまだ十分に大規模には導入されていません。その影響をどう評価するかも、まだ課題が残っています。

私たちは大陸上での取り組みを続けるだけでなく、劇的な手法も考えなければなりません。
同時に、どのように炭素を回収するのか、ほかの手段も模索する必要があります。 コミュニティに対して「これは必要な取り組みなのだ」と合意してもらう必要があります。そこには費用も伴います。
保全と保護の間で、私たちが持っている資源をどのように活用するかという解決策を見いださなければなりません。
最良の方法は、西側諸国に依存することでも、あるいは特定のリーダーシップに頼ることでもありません。
むしろ、コミュニティや現地の人々が解決策を実践し、そのうえで政府やリーダーがサポートする形こそが必要なのです。
さらに大切なのは、一般の人々にとってもこれは自分たちの利益になると理解してもらうことです。そして彼らと手を携えることができれば、物事を前進させられます。
ただし、多くの解決策を具体的に実行していく必要がありますし、私がパリ協定で最も強調したいのは、国際舞台においてボトムアップでソリューションを提示することなのです。それが重要なのです。


データ管理とシステム化
シャーロット・ハワード氏
もう1つ、会場からの質問に関して。もし理想的な政策フレームワークを思い描くとしたら、金融コミュニティが本気で資本を動員するために必要なものは何なのでしょうか?
具体的には、どんな要素の組み合わせが考えられますか?

イラナ・セイド氏 (パラオの国連大使兼常駐代表)
私は、多国間主義がいまだ大きな役割を担っていると考えています。あらゆる主要アクターがテーブルにつく必要があります。民間セクターも含め、特定のセクターに関してはかなり迅速な対応が可能だと思います。
たとえば、海洋に対するカーボンタックス(海上炭素税)の可能性などが議論されています。私たちもそれを調査してきましたが、大きな可能性があると思います。これは民間セクターだけの話ではありません。
シャーロット・ハワード氏
そこには公平性の問題なども絡んでくるでしょうか?
イラナ・セイド氏
海洋保護区から得られる恩恵もありますから、科学と政府が主導する形で段階的に進め、社会的合意(ソーシャルライセンス)を得ながら実施する必要があると思います。
政府は間違いなく一定の役割を果たしています。ただ、私たちはさらに物事を定量化し明確に示す力を高めなくてはなりません。
それは非常に価値あるアプローチで、保護自体の意義を伝えるうえでも大切ですし、例えば海洋保護区(MPA)を設定すると魚が増えて漁業収益が向上する、というような明確な経済的効果も期待できます。
そうした効果をきちんと捉えるためには、MRV(測定・報告・検証)システムやデータシステムを構築することが必要だと思います。
私たちのチームが行っている多くの作業は、各国や国際機関、あるいは開発途上国に対して、国家の経済勘定と互換性を持つようなデータシステムを構築する支援を行うというものです。
それが十分に管理されてこなかったのです。そうしたデータを整備することで、外部のコンサルタントや研究者が一時的に調査して終わり、という形ではなく、現地政府が主体的に取り組み、明確な証拠を提示できるようになるのです。
それは非常に実践的なステップの一つといえるでしょう。しかし実際、それがこれまで私たちが議論してきた多くのテーマを具現化する土台を築くのです。
こういった取り組みは何年も前から断続的に進められてきました。まだ言語化しきれていない部分もありますが、そこが解決策の領域なのだと思います。

―― 書籍/活動紹介 ――

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。
他の特集記事を見る

OTHER ARTICLE