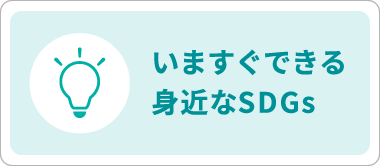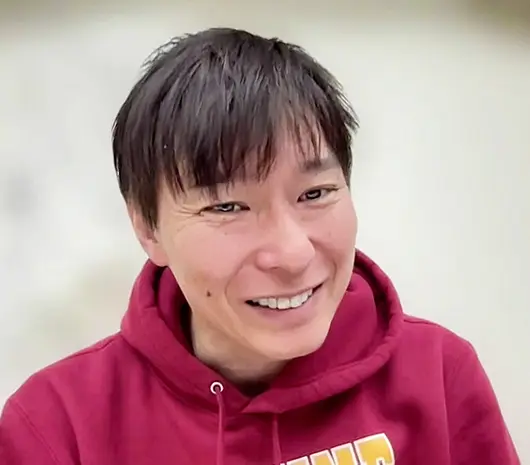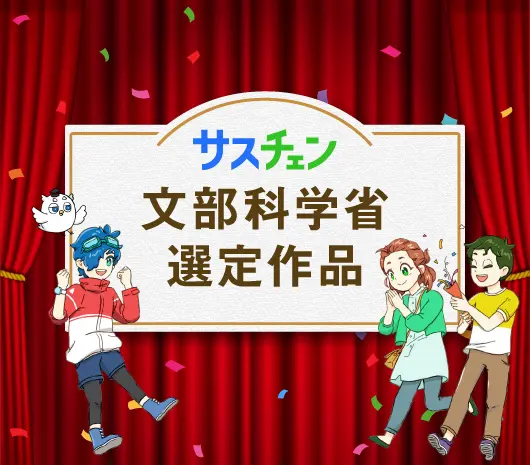港湾における脱炭素は可能か?海運を変える規制とテクノロジーとは--ワールド・オーシャン・サミット総力特集第6弾
2025年3月12〜13日に開催された、世界の海洋課題を議論する国際会議「第12回ワールド・オーシャン・サミット」。本特集は、その模様を多角的にお届けするレポートシリーズの第5弾です。
いま、海上輸送の未来が問われています。気候変動対策の最前線に立つ港湾は、巨額の脱炭素投資と規制の波にさらされながら、新たなエネルギーハブへと変貌を遂げようとしています。
今回は持続可能な海運の在り方を探るセッションをお届けします。
ワールド・オーシャン・サミットとは
ワールド・オーシャン・サミットは、持続可能は海洋経済に向けた行動を起こすことを目的に、世界中の政策立案者、ビジネスリーダー、科学者、NGO、技術開発者、投資家などが集結し、海洋環境を保護しながらも経済的に発展させる方法について議論する場です。

「グリーンからブルーへの移行における港湾と革新的技術」概要
海運の脱炭素化を推進する上で港はどれほど重要でしょうか? 海洋生態系を保護しながら経済成長を促進するチャンスはどこにあるのでしょうか?
テクノロジーと持続可能性を統合して海運バリューチェーンを変革する戦略的ハブとして、港湾はどのように進化しているのでしょうか?
■スピーカー
・エマ・コボス氏 バルセロナ港イノベーション・ビジネス戦略ディレクター


海上輸送の重要性
私たちの家にあるものの90%は海上輸送で運ばれているのに、輸送におけるCO₂排出量について話題になることがあまりありません。
実際、どれほどの排出量があるのでしょうか?海上輸送、つまり海運サプライチェーンに関わる排出量について見てみましょう。
全体のサプライチェーンで見ると約15%ですが、そのうち海上輸送の排出量はわずか3%です。実際には海上輸送が最も効率的な輸送手段であり、そこをもっと議論すべきだと思います。
海事セクターには直接的に1300万人の雇用があり、さらに間接的には3000万人の雇用が生まれています。
つまり港湾は非常に重要な役割を担っていますが、一方で排出量削減のプレッシャーも大きいです。海上輸送のCO₂排出量は世界全体の3%程度とはいえ、削減する意味は十分にあります。削減するのは妥当でしょう。そこで現在の港湾の状況がどのようになっているか、私たちが何をしているのかを大まかに説明したいと思います。
まず、ヨーロッパでは国際規制だけでなくEU独自の規制もあり、これらが脱炭素化を強く推し進めています。組織は人的リソースだけではなく、財政的にも持続可能である必要があります。ヨーロッパの港湾で起きていること、つまり脱炭素化は、資金の問題というより「やらなければならない」ものなのです。
他に選択肢はありません。ヨーロッパ中の港湾で、これを実行するために巨額の投資が進んでいます。


入港の管理が整備されていない
そこで、国際的・地域的な規制について手短にお話しします。
現在は新しい燃料や電化に向けて大規模投資が行われており、再生可能エネルギー資源を活用し、港湾がエネルギーハブになりつつあるのです。
これは私たちがもともと慣れ親しんだビジネスではありませんが、そこに関わる必要があります。そのために、人材を採用したり、船舶や技術面で取り組みを進めています。
私はずっと海運業界で働いてきましたが、いつも不思議に思っていました。
例えば自宅に届くそこまで重要でない荷物でさえ、DHLを使えば秒単位で追跡できるのに、数百万ドルやユーロ相当の貨物が入ったコンテナを扱う海運では、それが当たり前ではありません。追跡システムがまだ整っていません。
船舶の入港を効率化するソフトウェアがまだ十分に開発されていません。
つまり、完全には整備されておらず、現状入港手続きは効率的には運用されていないのです。 つまり今ある技術を考えても、海運の技術面や効率面ではまだ改善の余地が大きいのです。
ここにいる企業やスタートアップ、コンサルタントの方々にとっては、これは大きなビジネスチャンスと言えるでしょう。


海運も脱炭素化へ
それからエネルギー効率の向上の話です。例えばバルセロナ港の場合、20万人規模の都市と同等のエネルギーが必要なんです。信じられますか?
これを変える必要があります。従来のエネルギーを使い続けるわけにはいかないので、再生可能エネルギーへの転換が必要です。さらに、港に入ってくる船舶へのエネルギー供給方法も、サステナブルな形へと変えなければなりません。
さて、規制の話をしましょう。
全てではありませんが、IMO(国際海事機関)は脱炭素化を強く推進しています。さらにEUはより積極的に取り組んでいます。
EU排出量取引制度(ETS)は、ご存じの通り非常に厳しいものです。先ほどのパネルで「海運があまり注目されていない」といった話がありましたが、実際には私たちも海運が何をしてきたか注視していなかった面があります。
しかし現在では、その排出量が閾値を超えた場合、海運会社が支払いを行う必要があることは周知されるようになりました。


自動化がすすむ
また、EU炭素国境調整メカニズムもあります。EUが2025年1月に開始した制度で、アルミニウムや鉄鋼など特定の品目をEUに輸入するとき、排出されたCO₂に応じて企業が支払いを行う必要が出てきます。
つまり、原産国で排出されたCO₂を考慮するということです。これは全ての企業に適用される包括的な規制といえます。
こうした制度によって港湾はどうなるかというと、私たちもクライアントも脱炭素化に巨額の投資を行わざるを得ません。
では具体的にどのような対策を講じているのでしょうか?私たちは何をしているのでしょう?
技術面でいえば、サイバーセキュリティに大きく関わっている点が興味深いと思います。港湾は重要インフラであり、防衛の観点が最優先課題になっています。また、従来は非効率だった業務にAIを導入する取り組みも進んでいます。
さらに自動化も取り入れています。ただご存じのように、港湾での荷役(スティービドア作業)などは完全自動化が難しい部分があります。それでも部分的に自動化が進みつつあります。
現在の港湾が抱える課題の1つは、人材や知識が不足していることです。これらは私たちにとって新たなビジネス領域であり、全く未知の分野でもあります。 クライアントと連携しながらエネルギー転換を進める必要があります。


バルセロナをイノベーションセンターへ
また、港湾がエネルギーハブとして機能しなければならない状況にあります。
具体的にはアンモニアや水素などを扱う必要があり、あらゆる技術を試し、先頭を走る存在にならなければなりません。そして港湾内でこうしたさまざまなエネルギーをどのように効率的に配置するかを検討しています。
これは新たなビジネス領域でもあります。
つまり、港湾には「投資」と「イノベーション」という2つの要素が重要になってきます。あらゆるビジネスにおいて革新が必要で、私たちは投資面は得意なのですが、イノベーションに関してはまだまだ不得手な部分が多いと思います。
現在取り組んでいることの一例を紹介します。
バルセロナ港では、ブルーエコノミーに関するイノベーションハブを設立しています。海洋向けAIやデジタルツイン、新エネルギーや水素のプランなど、すべてを包括的に検討する場にしようとしているのです。
私たちは、イノベーションが盛んな都市バルセロナにおいて、EUにおけるブルーエコノミーのイノベーションセンターとなることを目指しています。ありがとうございました。

―― 書籍/活動紹介 ――

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。
他の特集記事を見る

OTHER ARTICLE