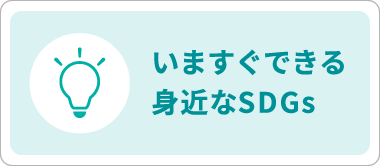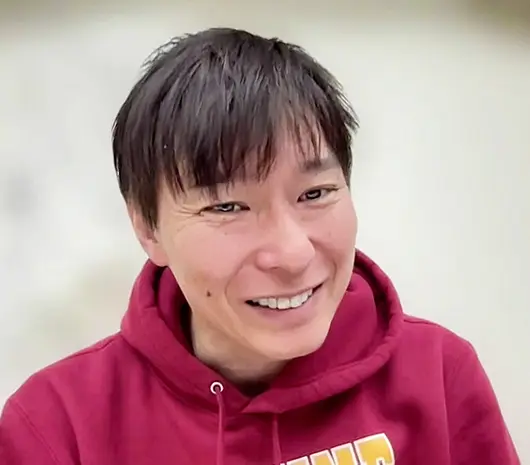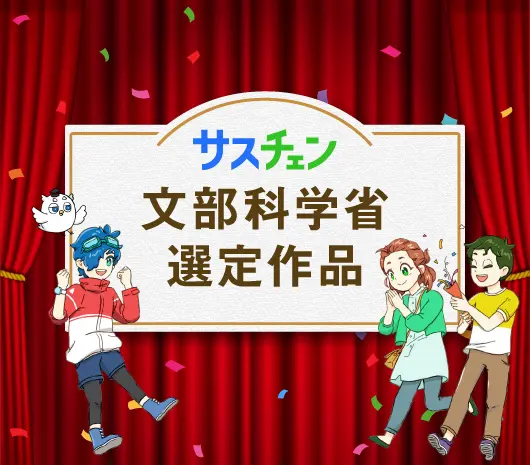ワールド・オーシャン・サミットが日本で初開催!パネルディスカッション「海洋汚染ゼロへの長い道のり」をレポート
海洋環境と持続可能な海洋経済を探る、第12回「ワールド・オーシャン・サミット」が3月12~13日に東京で開催されました。
同サミットには、海洋コミュニティに関わる企業・金融・政府・国内外の政策担当者・市民社会・学会など幅広い分野の方々が参加しました。
また、SDGsの目標14である「海の豊かさを守ろう」の2030年目標達成に向けて、新たな相乗効果、解決策、戦略を高めるプラットフォームを提供しています。
2日間にわたって開催されたサミットでは「気候変動」「生物多様性の損失」「持続可能な海洋資源にまつわる問題」など、10のテーマでパネルディスカッションやワークショップが行なわれました。
今回は、「海洋汚染ゼロへの長い道のり」というパネルディスカッションをレポートします。
ワールド・オーシャン・サミットとは
ワールド・オーシャン・サミットは、持続可能は海洋経済に向けた行動を起こすことを目的に、世界中の政策立案者、ビジネスリーダー、科学者、NGO、技術開発者、投資家などが集結し、海洋環境を保護しながらも経済的に発展させる方法について議論する場です。

「海洋汚染ゼロへの長い道のり」の概要
プラスチック汚染は、海洋の深刻な問題として広く知られています。
しかし、栄養塩類や下水から有毒化学物質に至るまで、海洋化学汚染の規模が科学的に解明されるにつれ、その影響はこれまで考えられていたよりもさらに深刻である可能性があることが明らかになりつつあります。
科学者、政府、投資家、企業、NGOは、海洋汚染を減らすためにどのように協力しているのでしょうか?
パネルディスカッション参加者
■司会
・チャールズ・ゴダード氏(エコノミスト・インパクト エディトリアル・ディレクター)
■パネリスト
・ヴィダール・ヘルゲセン氏(政府間海洋学委員会 ユネスコ事務局長)
・海野光行氏(日本財団 常務理事)
・スーザン・ガードナー氏(国際連合環境計画 生態系部門ディレクター)

海洋汚染問題解決に向けて、具体的な行動を
以下、対話形式でお届けします。
チャールズ・ゴダード氏(エコノミスト・インパクト エディトリアル・ディレクター)
昨年リスボンで行われたサミットに参加された方は「Back to Blue」プログラムをご存じかもしれません。 これは海洋汚染対策のロードマップ作成を目指すもので、数年間をかけて、ビジネスや科学、テクノロジーなど182のステークホルダーが協力し合って作成したものです。
その結果としてドラフト版のロードマップができあがり、国連環境計画(UNEP)からも実施に向けて推奨をいただきました。 両組織がこの計画を支援し、実行計画の策定に乗り出すと確認され、ここに至っています。
海野光行氏(日本財団 常務理事)

海洋汚染は気候変動・生物多様性と並ぶ深刻な脅威です。科学者の皆さんは産業排水などの汚染物質が深刻な影響を与えていることを知っています。この課題を可視化するために、データを集めるだけでは不十分なのです。ロードマップを作製して、具体的な行動に促すことが必要だと思っています。

各国の取り組みやデータを一元化
スーザン・ガードナー氏(国際連合環境計画 生態系部門ディレクター)
国連システム、とりわけUNEP(国際連合環境計画)は長年にわたり海洋汚染を主要課題として取り組んできました。 確かに進展はありますが、海洋問題というとプラスチックにばかり注目が集まる傾向が強いかもしれません。 ただ、このイニシアチブは既存の合意や、これまでに築かれたグローバルなコンセンサスをどう発展させ、さらに前に進められるのか、という点で重要です。
例えば、地域海条約(Regional Seas Conventions)は設立後ほどなくして策定され、海洋保護のプロトコルを取り入れました。 また、陸上活動が海洋に与える影響を防ごうとするGPA(陸上活動から海洋環境お保護に関する世界行動計画)も30周年を迎えていますが、100を超える国々が「陸での行動が海へ響く」という認識を共有したことは大きな成果です。
長年かけて、プラスチックのような持続的汚染物質への対策に力を合わせてきたことは評価に値しますし、最近採択されたグローバルな枠組みでも、核や化学物質の削減に関する大きな言及があります。 生計を守りつつ、汚染を減らすという方向で進めましょうというわけです。
断片的だった取り組みやデータを一元的にまとめ、アクセスしやすくするというのが今回のロードマップの狙いでもあります。 このイニシアチブが今後どんな役割を果たせるのか。 基本的にはグローバルな運動として、タスクの進捗管理やデータベースの強化が柱になるでしょう。 有効な戦略を立てるためには、あらゆる証拠やデータを総動員し、それを裏付けとして活用しなくてはなりません。

大きなスケールで連携を進める
ヴィダール・ヘルゲセン氏(政府間海洋学委員会 ユネスコ事務局長)
戦略的に言えば、 かなり包括的なプロセスを要します。 しかし、こうした議論はテクノロジー、政策、ビジネス、金融など、多様なプログラムを結びつけ、分野横断的な能力を高める助けになるでしょう。
生態系の健全性と環境コスト、地理的要素や農業分野などを結びつけ、境界を越えて考えねばなりません。 汚染物質などは海を越えて移動しますから、そのスケールに合わせた対策を再構築する必要があります。 中核的な考え方としては、既存の知識や条約をどう最適活用するか、という点が挙げられます。
チャールズ・ゴダード氏
リポジトリ(共有データベース)のガイドラインについてもご説明いただけますか?
ヴィダール・ヘルゲセン氏
先ほども言ったように、基本的な原則はさまざまなパートナーシップを統合することです。 プラスチック関連や海洋関連などのネットワークを束ねれば、データや知見を一体的に活用でき、不足している部分も洗い出せます。 さらに見落とされがちなコミュニティの知恵、先住民の知識などを取り入れれば、より優れた解決策を得られるはずです。 現在はドラフト段階ですが、そこから具体的な成果物がどう出てくるか、もう少し見守りたいですね。
今回のイニシアチブをどう進めるか、私としては皆さんに何かお手伝いできればと思います、 いずれにしても、ゼロから始めるわけではなく、既存の取り組みを強化する形です。
これは計画策定のための戦略をデザインする取り組みでもあります。 あらゆる要素を集約し、協力体制を築くのが非常に大事です。 スケジュール上、すでにドラフトの承認が出ており、評価ツールの立ち上げ案もあります。
科学的根拠に基づいた意思決定ツールを開発してきた歴史もありますし、データの問題こそ残るものの、各スケールで良い連携が進んでいます。 これはエキサイティングな展開で、さらに情報共有を進めていけると期待しています。
―― 書籍/活動紹介 ――

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。
他の特集記事を見る

OTHER ARTICLE