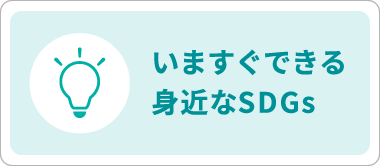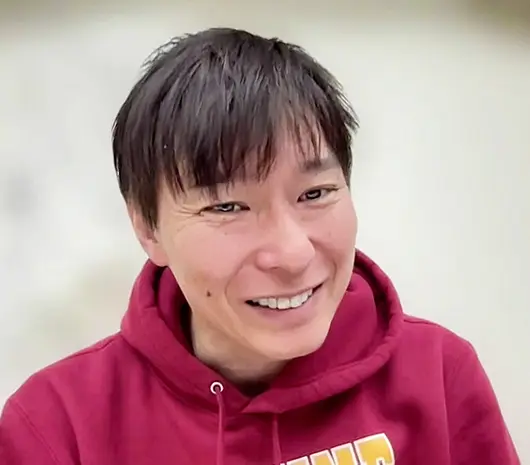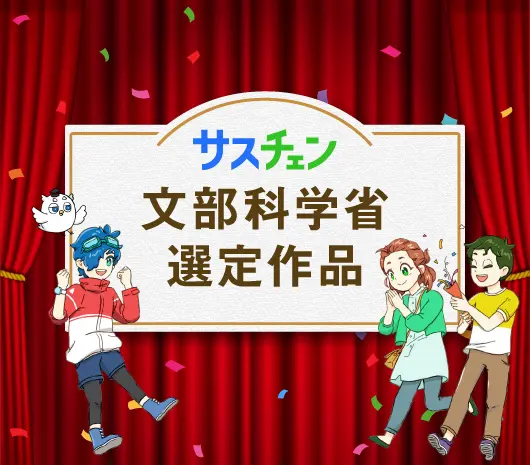海藻が秘めたポテンシャルとは?海藻産業を世界中で拡大するためにできること――ワールド・オーシャン・サミット総力特集第3弾
2025年3月12〜13日に開催された、世界の海洋課題を議論する国際会議「第12回ワールド・オーシャン・サミット」。本特集は、その模様を多角的にお届けするレポートシリーズの第3弾です。
日本でもよく親しまれている海藻が、気候変動対策やサステナブル素材として世界的に注目を集めています。
今後海藻にまつわる産業を拡大するには、どうすればよいのでしょうか?今回はパネルディスカッション「海藻革命の拡大」の模様をお届けします。
ワールド・オーシャン・サミットとは
ワールド・オーシャン・サミットは、持続可能は海洋経済に向けた行動を起こすことを目的に、世界中の政策立案者、ビジネスリーダー、科学者、NGO、技術開発者、投資家などが集結し、海洋環境を保護しながらも経済的に発展させる方法について議論する場です。

「海藻革命の拡大」の概要
日本は長年、海藻類を食べてきました。海藻類は現在、炭素隔離、肥料生産、包装素材として注目を集めています。
世界はアジアの海藻生産者から何を学べるでしょうか?この産業を世界規模で拡大するにはどうすればよいでしょうか?
■司会
・ジョナサン・バードウェル氏 エコノミスト・インパクト ポリシー&インサイト担当責任者
■パネリスト
・カルロス・デュラテ氏 キング・アブドラ科学技術大学海洋科学名誉教授
・桑江朝比呂氏 港湾空港技術研究所沿岸域環境研究グループ長 日本ブルーエコノミー協会会長
・ソウミヤ・バレンディラン氏 Sea6 共同創設者兼最高ビジネス責任者


海藻が海洋生態系を守る?
ジョナサン・バードウェル氏(エコノミスト・インパクト ポリシー&インサイト担当責任者)
皆さん日本にいらして海藻を召し上がったことがあるかもしれません。日本では海藻は主食の一つですが、いまや世界的に大きな注目を集めています。人の健康や食料システムへの活用だけでなく、炭素の吸収や肥料生産、産業用飼料、包装材、プラスチック代替など多くの可能性があるからです。
そこで今回は、海藻生産者の事例をもとに、海藻産業をどのようにグローバルに拡大してこうした利点を実現できるかを探っていきたいと思います。

海藻革命の拡大について議論するために、本日は以下の方々にお越しいただいています。
まず、カルロス・デュラテさん。キング・アブドラ科学技術大学海洋科学名誉教授です。次に、桑江朝比呂さんです。港湾空港技術研究所沿岸域環境研究グループに所属されていて、日本ブルーエコノミー協会の会長でもいらっしゃいます。そしてソウミヤ・バレンディランさん。Sea6 共同創設者兼最高ビジネス責任者です。
ではまずカルロスさんからお話を伺いたいと思います。
カルロス・デュラテ氏(キング・アブドラ科学技術大学海洋科学名誉教授)
ありがとうございます。まず海藻について少し説明したいと思います。海藻とひとくちに言っても、実は非常に多様な生物群です。海の「森」ともいえる存在で、世界全体でまとめると約7700万平方キロメートルもあると言われています。
光合成に大きく貢献し、海洋生態系で重要な役割を担っています。またアジア特に日本では、何世紀にもわたって大規模な海藻生産が行われてきました。
つまり海藻は決して新しいものではありません。日本では300年の歴史を持つ海藻養殖があります。一方、西洋諸国はようやく海藻の価値や可能性に気づき始めたところです。現在のデータによれば、世界の海藻養殖面積はおよそ2万平方キロメートル程度で、そのうち約50%が中国、約30%がインドネシア、約15%が日本、その他はアジアやアフリカに分散しています。
まだ規模は小さいため、食品やプラスチック代替素材、炭素吸収など、多岐にわたるニーズに応える潜在能力をさらに拡大していけるのです。

ジョナサン・バードウェル氏
それからカルロスさん、4月に天皇陛下から非常に名誉ある「ジャパンプライズ」を授与されると伺っています。おめでとうございます! あなたの研究についてもう少し、特に海藻の「グリーンサービス(自然の恩恵)」に関する部分を詳しく教えていただけますか?
カルロス・デュラテ氏
私の研究はもともと、海洋生態系がどのように機能し、人間活動がどのような影響を与えるのかを理解することが中心でした。しかしこの10年ほどは、気候変動や資源問題といったさまざまな課題を海洋がどのように解決できるかに焦点を当てています。
海藻はその有力な解決策の一つです。現在は、研究で得た知見を実際に活かすための技術開発や大規模な実証プロジェクトにも力を入れています。


ブルーカーボンクレジットの活用
ジョナサン・バードウェル氏
お話ありがとうございます。では次に桑江さんに伺います。日本では海藻養殖に300年の歴史があると聞いていますが、その生産規模や国際的な位置づけはどのようなものでしょうか。そして、日本で初めての「ブルーカーボンクレジット」制度を構築していると伺いましたが、その点についても教えていただけますか?

桑江朝比呂氏(港湾空港技術研究所沿岸域環境研究グループ長 日本ブルーエコノミー協会会長)
はい、ありがとうございます。日本では海藻は非常に身近で、寿司の海苔や昆布など、調味料としても多様に利用されています。歴史的にも古く、海藻養殖のための法的枠組みは7世紀にまでさかのぼります。しかし、近年は国内生産量が過去10年ほどで約2割減っているという課題もあります。
漁業や養殖業の高齢化も進み、中国やインドネシアなどとの競争も激しい状況です。一方、ブルーカーボンクレジット制度については、海藻やアマモ場など沿岸域の生態系がもつ炭素固定機能や生態系サービスを評価しようという試みで、現在約60件のプロジェクトがあります。
価格は一定ではありませんが比較的良い水準で、利益目的というより、地域の生態系保全に貢献したいというコミュニティや漁協が参加しています。若い漁師さんの中には、日々の仕事を気候変動対策につなげたいという意識を持つ人も増えていて、今後さらに発展していくと思います。

ジョナサン・バードウェル氏
ありがとうございます。ではソウミヤさんにお話を伺います。あなたは2010年にSeaSpicerを共同創業され、インドで海藻の洋上養殖を中心に取り組んでいると聞きました。どのように始められて、現在どのくらいの規模になっているのか、また資金面を含めた課題などについて教えていただけますか?
ソウミヤ・バレンディラン氏(Sea6 共同創設者兼最高ビジネス責任者)
もちろんです。私たちは2010年に大学卒業したばかりの4人で会社を立ち上げました。インドや世界に大きなインパクトを与えたいという思いから始まりました。さまざまな可能性を調べましたが、陸上でのバイオマス生産には限界があると気づき、海藻養殖に大きな可能性を見い出したんです。
最初は私たち自身、海藻がどういうものかさえ知らず、5時間かけて海藻を見に行ったくらいです(笑)。
その後、種付けや収穫を機械化するなど、技術開発を進めてきました。海藻養殖は、まるで1万年前の農業のように手作業が中心で、そこにイノベーションを取り入れれば大きく拡大できると考えました。現在はインドネシアでおよそ100ヘクタールの養殖場を運営し、加工や輸送、海藻から多様な製品を作るバリューチェーン全体を構築中です。
資金調達は苦労しましたが、幸いにもインパクト投資家や政府の支援を受けることができました。それでもまだ始まったばかりという感じですが、10年前と比べれば状況は大きく改善しており、世界的な関心も高まっていると実感しています。


海藻養殖のインフラ整備を
ジョナサン・バードウェル氏
ありがとうございます。ここで再びカルロスさんに伺いますが、もし海藻養殖を大規模に拡大した場合、何かネガティブな影響は考えられるでしょうか。例えば生物多様性への影響など、心配すべき点はありますか?
カルロス・デュラテ氏
大規模な海藻養殖の拡大は十分起こり得ると思います。食料安全保障に役立ち、炭素の観点でもプラスになり、淡水や肥料、農薬などの使用も最小限で済む作物だからです。
ただし、例えば数百万平方キロメートル規模にまで広げるなら、海洋空間のガバナンスは不可欠です。何の計画もなく海域を占有してしまえば、海藻の大規模な流出や外来種問題などが起きる可能性もあります。
それでも総合的に見れば、海藻には大きな可能性があります。最大の障壁は制度面でしょう。許認可や、既存の石油・ガス事業、航路、地域コミュニティなどとの利害調整が難しいのです。また、洋上での海藻養殖には技術開発が必要で、洋上風力のように大規模なインフラを整えることが視野に入ります。
年20%程度の成長率で拡大し、適切なインセンティブやゾーニングを行えば、責任ある発展が可能だと思います。また、食用だけでなく高付加価値の抽出物やバイオポリマーなど、多方面で収益源を作るビジネスモデルが求められます。


クレジット制度を環境保全に活用
会場質問
ライアンと申します。桑江さんにお伺いしたいのですが、日本のブルーカーボンクレジット制度は成功例としてよく挙げられます。その最近の取引価格や、世界的な水準との比較について教えていただけますか?

桑江朝比呂氏
現在およそ60のプロジェクトがあり、炭素吸収量の正確な評価は続けています。クレジットの価格は一定ではありませんが、概ね妥当な水準です。中には高い価格で買い取る企業もありますが、地域コミュニティの中には、売って収益を得るよりも、将来世代のために保有したいという動きもあります。
特に若い漁師さんは、日々の漁業を環境保全と結びつける新しい方法として、このクレジット制度を捉え始めています。さまざまな状況がありますが、全体としては前向きに進んでいます。

ジョナサン・バードウェル氏
本日は興味深いお話をありがとうございました。今回の議論から言えるのは、海藻には非常に大きな可能性があるということです。拡大しやすく、負の外部性が少なく、新しい用途への応用も進んでいます。皆さんのお話にとても刺激を受けました。ぜひ大きな拍手をお願いします。

■前回までの記事はこちら
ワールド・オーシャン・サミットが日本で初開催!パネルディスカッション「海洋汚染ゼロへの長い道のり」をレポート – SDGs特集記事|リンクウィズSDGs
汚染、騒音、海洋動物との衝突――海運業界の「負の影響」を減らすには?ワールド・オーシャン・サミット総力特集第2弾 – SDGs特集記事|リンクウィズSDGs
―― 書籍/活動紹介 ――

SDGsはもちろんのこと、サステナブル・エシカルな視点から記事を制作する編集者・ライターの専門チームです。社会課題から身近にできることまで幅広く取り上げ、分かりやすくお伝えします。
他の特集記事を見る

OTHER ARTICLE