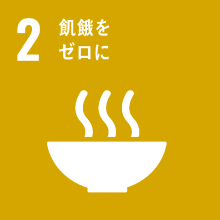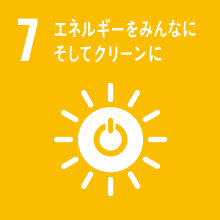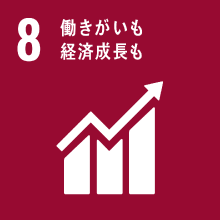| SDGs 17の目標 |
関連する 科目 |
教科書項目 | 関連する 内容 |
|---|---|---|---|
|
貧困をなくそう |
社会 |
【教育出版社】 小学社会 3:「農家のしごと」 小学社会 5:「自然条件と人々のくらし」 小学社会 5:「未来を支ささえる食料生産」 小学社会 5:「これからの食料生産」 小学社会 6:「平和で豊かな暮くらしを目ざして」 小学社会 6:「戦争と人々の暮くらし」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で農業や食料の生産・暮らしにかかわる学習をする際に、動画を通じて世界中にはあらゆる場所で、戦争や紛争・自然災害や家庭環境などの理由から「極度にまずしい人」がいて学校に通えなかったり生きることが難しい子供達がいることを学べます。 SDGS目標1「貧困をなくそう」で掲げている「貧困」状態にある人々を半減することの解決策について、考えを深めます。 |
|
飢餓をゼロに |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 3:「農家のしごと」 小学社会 5:「自然条件と人々のくらし」 小学社会 5:「未来を支ささえる食料生産」 小学社会 5:「これからの食料生産」 小学社会 5:「日本の国土と世界の国々」 小学社会 6:「平和で豊かな暮くらしを目ざして」 小学社会 6:「戦争と人々の暮くらし」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で農業や食料の生産・暮らしにかかわる学習をする際に、動画を通じて国の情勢や自然環境・災害・戦争などの要因で食料が行き渡っていない「飢餓」である人が多くいる一方、先進国をはじめとした国々で大量の食べ物が廃棄されている問題があることを学べます。 SDGS目標2「飢餓をゼロに」は自然環境を維持しながら食料生産を行い、飢餓をなくす包括的な目標です。フードロス削減や、フェアトレード認証マークの商品を購入するなど身近なところにも解決のカギがあります。 |
|
すべての人に健康と福祉を |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 6:「憲法とわたしたちの暮らし」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で「憲法」など国の決まりやしくみについて学習する際に、私たちが住む日本国では国民一人一人が健康で生きられるよう健康保険証などの医療制度・行政の仕組みがあるが、世界のすべての人が同じ制度を使用できるわけではなく、制度がない為に適切な医療を受けれずに衛生環境などの要因で命を落とす人も世界中には数多くいることを学べます。 SDGS目標3「すべての人に健康と福祉を」は、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確実にし、福祉を推進するという目標を掲げています。 |
|
質の高い教育をみんなに |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 6:「憲法とわたしたちの暮らし」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で「憲法」など国の決まりやしくみについて学習する際に、動画を通じて日本国の憲法においては、教育を受ける権利は法の元ではみな平等と保証されているが、世界の中では貧困や戦争、また様々な要因で教育を受ける環境が整わず小学校に通えていないこども達が多くいることを学べます。 SDGS目標4「質の高い教育をみんなに」では、すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進することを目指しています。 質の高い教育は、持続可能な生活の維持能力を与え、貧困の連鎖を断ち切るだけではなく、不平等の是正やジェンダーの平等などの達成にも貢献します。 |
|
ジェンダー平等を実現しよう |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 6:「憲法とわたしたちの暮らし」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で「憲法」など国の決まりやしくみについて学習する際に、動画を通じて日本の憲法の様に「性別や社会的身分などに関係なく法の元ではみな平等で人権を保証されている」といった定めがない世界の国では、女児は学校にいけなかったり 未成年の早期結婚や強制結婚、女性がつける仕事や場所が少ないなどの有害な慣行・差別があることを学べます。 SDGS目標5「ジェンダーを平等に実現しよう」では女性や女児に対するあらゆる形態の差別・暴力の撤廃を掲げています。 未成年の早期結婚や強制結婚、女性器切除などの有害な慣行をなくすこと、また無報酬の育児・介護や家事労働の評価などが盛り込まれています。 |
| 保健 | 【光文書院】 小学保育4・5:「体の発育と健康」 小学保育6:「心の発育と健康」 |
保険体育の授業で「体」と「こころ」の発育と健康を学習する機会に、性別による多様性について学べます。 | |
|
安全な水とトイレを世界中に |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「水はどこから」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で生活に必要な「水」ができるまでの仕組みを学習する際に、動画を通じて日本では蛇口をひねれば出てくる水ですが、世界には水が不足していたり・トイレがないことで衛生環境や健康・食料の生産など人々の生活に悪い影響をあたえていること、世界には水の問題を抱えてる人々が多くいることを学べます。またなぜ水が不足しているかの原因を知ることができます。 SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」は、すべての人が安全に水を飲めるようにすること、トイレを利用できるようにすることに加えて、水不足や水質向上など水に関するあらゆる問題を解決する内容となっています。 |
|
エネルギーをみんなに そしてクリーンに |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「水はどこから」 小学社会 4:「くらしと電気」 小学社会 5:「森林とともに生きる」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科では水や森林の有効さ・大切さ、理科では電気のしくみやその利用法など私たちの生活をどれだけ便利にしているかを学ぶ中で、電気(エネルギー)のない国では、生活の為に木を燃料とするため森林伐採が進んでいて、木を燃やすことで排出される二酸化炭素で自身の健康を損ねたり、また地球温暖化にも大きな影響を与えている現状があることを知れます。 SDGs目標7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」では、すべての人が近代的なエネルギーを使えるようにするとともに、環境に負荷をかけないクリーンな再生可能エネルギーを増やすために、私たちが具体的にするべきことを示した目標です。太陽や風など自然の力で作られる「再生可能なエネルギー」を新たに増やすなど、技術と工夫で限りある資源を守り続けることが大切です。 |
| 理科 | 【大日本図書】 たのしい理科 3:「10.電気の通り道」 たのしい理科 4:「3.電池のはたらき」 |
||
|
働きがいも 経済成長も |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
世界の人口は増え続けていて、働ける場所を増やすことが求められていますが、若い人が働き先、児童労働など多くの問題を抱えています。 すべての人々が働きがいのある社会を目指しながら経済発展を実現させるためには「ディーセント・ワーク」や「フェアトレード」に関わる仕組みを整えながら、国や人のさまざまな格差を少なくする必要がありることを学べます。 SDGs目標8「働きがいも経済成長も」とは、環境と両立しうる持続的な経済成長と、その担い手としての労働者が働きがいを持ち、また生きていくのに必要な賃金を得られる社会の実現を目標としています。 |
|
産業と技術革新の基盤をつくろう |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「地震にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「水はどこから」 小学社会 5:「森林とともに生きる」 小学社会 5:「くらしと産業を変える情報通信技術」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
まちづくりや自然との共存、産業について学習する中で、人々が貧困から抜け出し、経済を発展させるためにはインフラを整えながら、働ける場所を作り出す必要があり、そのためにはまず、都市部と地方のインフラ格差をなくす必要があることを学べます。持続的に経済を発展させるために「グリーンインフラ」など、地球環境に配慮したインフラ作りが必要とされています。 SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」とは、だれもが安心して快適に暮らせる社会をつくるために、暮らしを支える強靭(レジリエント)なインフラを構築するとともに、技術革新で新たな価値を作り、持続可能な産業を構築することを掲げた目標です。 |
|
人や国の不平等をなくそう |
総合 | 【教育出版社】 小学社会 6:「戦争と人々の暮くらし」 小学社会 6:「平和で豊かな暮くらしを目ざして」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科では戦争と平和について学習する中で、動画を通じて世界の中では国籍・性別・人種・民族・宗教の違いで差別が起きていて数多くの地域で争いにつながり国や人々の間で経済格差による不平等が広がっていることを学べます。 道徳の授業で「親切,思いやり」「友情,信頼」「公正,公平,社会正義」「国際理解,国際親善」といった心の学びを受ける際に、動画を通じてかたよった不平等な考え方を少なくし相手の立場や文化の違いを理解すること、弱い立場の人に支援が行き渡る仕組みが必要とされていることを学べます。 SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」とは、国内や国家間で起こる不平等をなくすために示された目標です。 所得格差を是正し、すべての人が人種や性別・階級などを理由に差別されることのない平等な世界を目指します。 |
| 道徳 |
「親切,思いやり」 「友情,信頼」 「公正,公平,社会正義」 「国際理解,国際親善」 |
||
|
住み続けられるまちづくりを |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「健康なくらしとまちづくり」 小学社会 4:「ごみはどこへ」 小学社会 4:「自然災害にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「地震にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「水害にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「昔から今へと続つづくまちづくり」 小学社会 4:「昔のよさを未来に伝つたえ」 小学社会 4:「自然を生かしたまちづくり」 小学社会 4:「国際交流がさかんなまちづくり」 小学社会 5:「自然災害とともに生きる」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で人々が自分たちが住む町について、安全に生活できる為のしくみ作りやごみ処理・災害対策などを学習する際、動画を通じて世界では都市部への人口集中によるゴミの増加や、貧しい人と豊かな人の格差、治安の悪化など数多くの問題を抱えていることを学べます。 SDGS目標11「住み続けられるまちづくりを」では、地球上に住む人間すべてが住み続けられるよう、さまざまな課題に立ち向かいながらまちづくりを進めていくことを掲げています。 安心して人々が暮らせるようにするには、災害につよく立場の弱い人たちも使える施設をそなえた街づくりや、地球環境にやさしいゴミ処理を実現することが大切です。 |
|
つくる責任 つかう責任 |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「健康なくらしとまちづくり」 小学社会 4:「ごみはどこへ」 小学社会 4:「地震にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「水害にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「昔から今へと続つづくまちづくり」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で人々が自分たちが住む町について、安全で快適に生活できる為の整備やごみ処理・災害対策などを学習する際、また家庭科で物やお金の使い方を学習する際に、動画を通じて人々は生活をより豊かにするために環境のことを考えず、経済を優先してより安いものを大量に作り必要以上に物を作りすぎ大量に廃棄が行われるようになり地球の環境に大きな影響を与えていること、地球環境にやさしい物づくりや再利用してゴミを出さない仕組みづくりが求められていることが学べます。物をリサイクル・リユースしたりする意義が分かります。 SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」とは、限りある地球の資源を守るため、持続可能な生産と消費のバランスを形成することです。省エネと資源効率の促進やインフラ整備で人々の生活の質の向上し、環境にやさしく、より少ないものでより多くを作り、より良い未来に変えていくことへの気づきを生み出します。 |
| 家庭科 | 【東京書籍】 新編 新しい家庭 5:「4.持続可能な社会へ 物や金の使い方」 新編 新しい家庭 5:「6.物を生かして住みやすく」 |
||
|
気候変動に具体的な対策を |
理科 | 【大日本図書】 たのしい理科 4:「1.天気と気温」 たのしい理科 4:「5.雨水のゆくえ」 たのしい理科 5:「1.天気と情報(1)天気の変化」 たのしい理科 5:「4.天気と情報(2)台風と防災 たのしい理科 5:「6.流れる水のはたらきと土地の変化」 たのしい理科 6:「8.土地のつくりと変化」 たのしい理科 6:「11.生物と地球環境」 |
理科では天気など気候について、社会科ではまちづくりの学習する際に、動画を通じて地球環境の変化から年々気候が変化しその影響で人々の生活に起こっている様々な問題や災害について、またそういったことが起こっている原因について学べます。 家庭科では、気候変動の要因の一つとして挙げられている「ごみ問題」や「食品ロス」について、調理実習や省エネなどの暮らしの工夫で解決できることに関連して学べます。 SDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」では、温室効果ガスの排出を原因とする地球温暖化現象が招く世界各地での気候変動やその影響を軽減することが目標です。 これを実際に実現するためのターゲットと実行手段を定め、取り組んでいます。 |
| 社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「自然条件と人々のくらし」 小学社会 4:「地震にそなえるまちづくり」 小学社会 4:「水害にそなえるまちづくり」 小学社会 5:「自然災害とともに生きる」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
||
| 家庭科 | 【東京書籍】 新編 新しい家庭 5:「5.食べて元気!ご飯とみそ汁」 新編 新しい家庭 5:「11.夏をすずしくさわやかに」 新編 新しい家庭 5:「6.物を生かして住みやすく」 新編 新しい家庭 5:「14.冬を明るく暖かく」 |
||
|
海の豊かさを守ろう |
理科 | 【大日本図書】 たのしい理科 6:「11.生物と地球環境」 |
理科で海には様々な生物が生息していることを学びますが、社会科ではその海に、私たちの生活を営む中ででペットボトルなど大量のごみが流されていることを学習します。動画を通じて世界の海では大量のプラスチックゴミが毎年流れ続けていてこのままのスピードで海にプラスチックゴミが増え続けると、2050年には海にいる魚の量よりもプラスチックゴミの量が上回ると予想されています。健康な体を維持する為に必要な食事において海産物が生息している海が、私たちが捨てるプラスチックなどで汚染されその影響で最終的には私たちの健康にも影響してくる可能性があることを学べます。 SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」とは、失われつつある海の豊かさを守り、海や海洋資源を持続的に利用するために掲げられた目標です。 さまざまな問題を抱える海の自然環境を守り、生態系を維持していくためには、使い捨てが中心のプラスチック容器や包装ゴミを減らす取り組みや、石油や石炭といった化石燃料を使用するエネルギーから、太陽光や風力発電といった再生可能なエネルギーの使用を増やしていくことが必要です。 |
| 社会 | 【教育出版社】 小学社会 4:「ごみはどこへ」 |
||
| 家庭 | 【東京書籍】 新編 新しい家庭 5:「5.食べて元気!ご飯とみそ汁」 新編 新しい家庭 6:「10.朝食から健康な 1 日の 生活を」 新編 新しい家庭 6:「13.まかせてね 今日の食 事」 |
||
|
陸の豊かさも守ろう |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 5:「自然災害とともに生きる」 小学社会 5:「森とともに生きる」 小学社会 5:「自然災害とともに生きる」 小学社会 5:「環境とともに生きる」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科や理科で森林の役割や有効さ、必要性を学習する際に、動画を通じて世界では森林破壊や大規模化する自然災害により30年間で日本の面積5つ分もの森林が失われていること、そこに住む動植物にさまざまな影響が出ていること、このままのスピードで森林が減少すると2050年には地球上の生物の約4分の1が失われると予想されいることを学びます。陸の自然環境を守り、生態系を維持していくためには、植林を通して森林を増やしたり、適切に森林を管理し、そこから生まれた製品を利用する仕組みが求められています。 目標15「陸の豊かさを守ろう」は、陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止すること、つまり、陸の豊かさを守り、砂漠化を防いで、多様な生物が生きられる環境を守ることを目指しています。 |
| 理科 | 【大日本図書】 たのしい理科 5:「2.生命のつながり(1)植物の発芽と成長」 たのしい理科 5:「5.生命のつながり(3)植物の実や種子のでき方」 たのしい理科 5:「6.流れる水のはたらきと土地の変化」 たのしい理科 6:「5.生物どうしの関わり」 たのしい理科 6:「8.土地のつくりと変化」 たのしい理科 6:「11.生物と地球環境」 |
||
|
平和と公正をすべての人に |
社会 | 【教育出版社】 小学社会 6:「戦争と人々の暮くらし」 小学社会 6:「平和で豊かな暮くらしを目ざして」 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で戦争や平和、国際協力について学ぶ際に動画を通じて、世界ではすべての国で家庭における子供への体罰や暴力を法律で全面的に禁止している訳ではないことを知り、紛争だけではなく犯罪や日常的な暴力から市民や弱い立場である子供を守るためには公正な法律や制度が整った社会づくりを行う必要があることを学べます。 SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」とは、争いのない平和な社会を実現するために掲げられた目標です。 誰もが受け入れられ、法律や制度で守られる未来を目指しています。 また、あらゆる争いをなくすことも大きな課題です。 |
|
パートナーシップで目標を達成しよう |
総合 | 【教育出版社】 小学社会 6:「地球規模の課題の解決と国際協力」 |
社会科で地球規模の課題や解決方法・国際協力について学ぶ際に、動画を通じて北欧ではクリーンエネルギーを活用して自給自足ができるエコビレッジの導入や、小学校の授業で自然環境の保護に必要なこと・SDGsの内容を理解し政府や地域と協力しやすい環境が整えられていること、深刻な先進国と途上国との経済格差への取り組みや貧困や飢餓に困っている人を助けるためには一つの国だけの力では限界があることを学べます。今、世界中の国々のパートナーシップが必要とされているのです。 SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」とは、SDGsの目標達成をスムーズにすべく国や機関など「あらゆる場面で助け合おう」というものです。 |